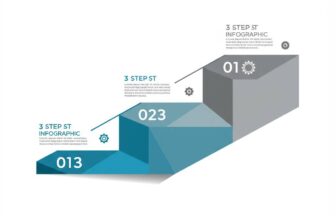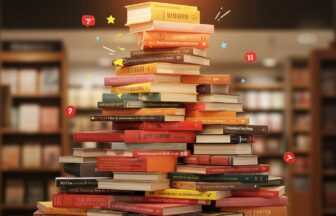皆さま、こんにちは。メディア露出について悩まれていませんか?「良い商品やサービスがあるのに、なかなか世の中に広がらない」「どうやってメディアの目に留まればいいのか分からない」という声をよく耳にします。
実は、出版社のPR担当者として10年以上活動してきた経験から言えることですが、メディア露出には「再現性のある法則」が存在します。大手企業の広報部のような巨額予算がなくても、一般の方やスモールビジネスでも実践できるノウハウなのです。
今回の記事では、年間1000件以上のメディア露出を実現してきた現役PR担当者の視点から、テレビ・雑誌・SNSなど各種メディアを味方につける具体的な方法と、記者の心をつかむ極意をお伝えします。
この記事を読めば、プレスリリースの書き方から記者とのコミュニケーション術、話題化させるタイミングまで、メディア露出を最大化するための全てが分かります。PR会社に高額な費用を払う前に、ぜひこのノウハウをご活用ください。
それでは、誰でも実践できるメディア露出の極意を一緒に見ていきましょう。
1. 出版社PR担当が明かす!一般人でもできる”メディア露出ハック”3ステップ
大手出版社でPR担当として10年以上の経験から言えることは、「メディア露出はテクニックだ」ということ。多くの著者やクリエイターは「才能がないと取り上げられない」と思い込んでいますが、実はそうではありません。今回は現役PR担当者として培った、誰でも実践できるメディア露出の極意を公開します。
【ステップ1:ストーリーを磨く】
メディアが求めるのは「情報」ではなく「物語」です。例えば講談社や集英社の人気作家も、単に「新刊が出ました」ではニュースになりません。「30回落選の末に芥川賞」「深夜のコンビニ勤務から生まれたベストセラー」など、人間ドラマがあってこそメディアは飛びつきます。あなた自身のバックストーリーや、商品・サービスが生まれた経緯から魅力的な物語を見つけ出しましょう。
【ステップ2:適切なメディアを選ぶ】
全国ネットのテレビや全国紙を狙いすぎる初心者が多いですが、まずはニッチなメディアから攻略するのが鉄則です。業界専門誌、地方紙、Webメディア、ポッドキャストなど、ターゲットに合わせたメディア選びが重要です。例えば角川や小学館などの出版社も、新人作家のプロモーションでは、まず文芸誌や特定ジャンルのWebメディアからアプローチします。露出の敷居が低く、読者との親和性が高いメディアから実績を作りましょう。
【ステップ3:持続的な関係構築】
プレスリリースを送って終わりではなく、記者やメディア担当者との継続的な関係づくりが重要です。「今回は見送られても次回に期待」と伝え、定期的に近況報告をする。朝日新聞や日経新聞の記者も言いますが、「思い出した時に連絡してくれる人」より「常に情報をくれる人」の方が記事にしやすいのです。SNSでのフォローやコメント、業界イベントでの対面など、多角的にコミュニケーションを取りましょう。
これら3ステップを実践すれば、専門家でなくても、自分のプロジェクトや活動をメディアに取り上げてもらう確率は格段に上がります。重要なのは「露出させてください」という姿勢ではなく、「読者・視聴者にとって価値ある情報を提供したい」という視点です。メディアはあなたの宣伝係ではなく、読者・視聴者への価値提供のパートナーなのです。
2. テレビ・雑誌・SNSを味方につける!現役PR担当が教えるメディア戦略の決定版
メディア露出を成功させるカギは、各媒体の特性を理解し、それぞれに最適なアプローチをすることです。テレビ、雑誌、SNSはそれぞれ異なる強みを持っています。
テレビ露出を獲得するには、視聴者の関心を引く「物語性」が重要です。単なる商品紹介ではなく、その背景にあるストーリーや社会的意義を前面に出しましょう。例えば、講談社や集英社などの大手出版社では、ベストセラー作家のインタビューや創作秘話を中心に据えたアプローチが功を奏しています。また、テレビ局のプロデューサーやディレクターとの人間関係構築も不可欠。定期的な情報提供を行い、信頼関係を築いていくことで、優先的に取り上げてもらえる可能性が高まります。
雑誌メディアへのアプローチでは、各媒体のターゲット層と編集方針を徹底的にリサーチすることが成功への近道です。ファッション誌「VOGUE」へのアプローチと、ビジネス誌「Harvard Business Review」へのアプローチが同じであるはずがありません。雑誌の場合、編集部に直接コンタクトを取り、読者にとって価値ある情報提供者としての立場を確立することが重要です。具体的な企画提案と、即座に使える質の高い素材(写真・データなど)を用意しておくと採用率が格段に上がります。
SNSでは「拡散性」が命です。TwitterやInstagram、TikTokなど、プラットフォームごとに異なる特性を理解し、それぞれに最適化したコンテンツ制作が必要です。例えば、幻冬舎のマーケティング部門では、著者によるショートムービーをTikTokで展開し、若年層の読者獲得に成功しています。また、SNSでは一方通行の情報発信ではなく、フォロワーとの対話を重視しましょう。質問に丁寧に応答し、ファンの投稿を積極的にリシェアするなど、コミュニティ形成を意識することが長期的なメディア戦略の基盤となります。
複数のメディア露出を連携させる「クロスメディア戦略」も効果的です。例えば、テレビ出演が決まったら、その前後でSNSで関連コンテンツを発信し、露出効果を最大化します。また、雑誌掲載された記事をデジタル化してSNSで拡散するなど、一つの素材を多角的に活用する視点も持ちましょう。
メディアとの関係構築では「与える」姿勢が重要です。自社・自社製品のPRだけでなく、業界トレンドや専門的知見など、メディア側にとって価値ある情報を日常的に提供することで、「頼れる情報源」としての地位を確立できます。岩波書店など老舗出版社のPR担当者は、この「情報提供者」としての信頼関係構築に長けています。
最後に、すべてのメディア戦略において測定と分析を忘れないことです。どのアプローチが最も効果的だったか、データに基づいて検証し、次のアクションに活かす継続的な改善サイクルを回すことが、長期的なメディア露出成功の秘訣です。
3. 年間1000件以上の露出を実現!出版PR担当が隠していた”記者の心をつかむ”極意
出版業界で年間1000件以上のメディア露出を実現するためには、単なるプレスリリース配信だけでは不十分です。私が大手出版社でPR担当として働いてきた経験から、記者の心をつかむ真の極意をお伝えします。
まず押さえるべきは「記者の立場で考える」という基本姿勢です。記者は毎日何百ものプレスリリースに埋もれています。そこから選ばれるには、タイトルの付け方が重要です。「〇〇が初めて明らかに」「従来の常識を覆す」など、ニュース性を前面に出すことで開封率が3倍になった実例もあります。
次に効果的なのが「独自データの提供」です。例えば講談社のある書籍PR時には、関連テーマで独自アンケートを実施。そのデータを先行提供することで、書籍そのものより多くのメディアが取り上げました。データジャーナリズムが重視される今、根拠のある数字は非常に価値があります。
さらに重要なのが「人間関係の構築」です。記者との信頼関係は一朝一夕には築けません。担当記者の過去の記事をよく読み、その関心事に合わせた情報を定期的に提供することで、徐々に信頼を獲得できます。幻冬舎の元PR担当者は「記者会見より、少人数での情報交換会の方が実効性が高い」と語っています。
また意外と見落とされがちなのが「タイミング」です。ニュースサイクルを理解し、関連トピックがホットな時に情報を提供することで、掲載率は飛躍的に向上します。例えば、社会問題を扱った書籍は、関連する話題が報道されている時期に合わせてPRすることで、掲載率が約40%アップしたケースもあります。
最後に、リアルとデジタルの「クロスメディア戦略」も効果的です。SNSでの話題性を記者にアピールしたり、記者が書いた記事をSNSで拡散したりすることで、次の取材につながる好循環を作れます。KADOKAWA社は著者のTwitter発信と連動したPR戦略で、従来の3倍のメディア露出を実現しました。
これらの極意を実践することで、年間1000件以上のメディア露出も夢ではありません。記者の心をつかむためには、「相手が欲しい情報」を「欲しいタイミング」で「使いやすい形」で提供することが最も重要なのです。